|
リストラ天国 ~失業・解雇から身を守りましょう~
HomePage https://restrer.sakura.ne.jp/
|
1854
エアー2.0(小学館文庫) 榎本憲男
◇2025年7月前半の読書と感想、書評(巡査長 真行寺弘道)
2020年東京オリンピック開催以前の東京や、原発事故で帰宅困難地区がある福島が舞台となっています。
肉体労働者の青年が新国立競技場の建設工事で、他の労務者からイジメに遭っていたパッとしない老人と知り合いになります。
しかしその老人は、あとでその謎が明かされますが、自ら最先端の市場予測システムを開発していて、それをその老人の指示に従って政府へ売り込み、莫大な資金を得ることになります。
そこで青年は得た資金を、青年の出身地で原発事故で立ち入りが規制されている福島のエリアを国に特別自治区に指定してもらい、そこに新たな起業家に投資し、福島の復興計画をスタートさせます。
東日本大震災や原発事故をテーマにした小説はいくつか読みましたが、これは新しい切り口で、しかもSF的な要素もあり面白いです。
タイトルはその完全な市場予測システムの名称で、ソフトウエアとハードウェアがセットになったモノという立て付けです。
原発事故で壊滅した地域を再興するために、原発でしか得られない莫大な安定した電力が必要なシステムという組み合わせがなかなか矛盾をはらんでいてユニークです。
2024年には、弱点を克服しスケールアップした続編の「エアー3.0」が出版されています。
★★☆
◇著者別読書感想(榎本憲男)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
警告(上)(下)(講談社文庫) マイクル・コナリー
本作はその中でも珍しい記者を主人公とした「ジャック・マカヴォイシリーズ」に属する作品で、「ザ・ポエット」(1996)、「スケアクロウ」 (2009)に続き11年ぶりの3作目です。
原題は「Fair Warning」で、2020年に米国で出版され、2021年に和訳版が出版されています。
直訳すると「真っ当な警告」と、タイトルはほぼ直訳ですが、もうひとつ、主人公の記者が在籍する実在するアメリカの消費者問題を扱うWEBニュースサイト「Fair Warning」社そのものをタイトルに使っています。
文庫のあとがきで知りましたが著者はこのニュースサイトの取締役でもあり、社長は実在の社長の名前を使っていることから、このサイトのPRにもなっているのでしょう。うまいやり方です。
このニュースサイトは刑事事件を追いかけるようなメディアではありませんが、そこの記者として勤めている主人公が、過去に一夜を共にしたバーで知り合った女性が殺されたことから参考人として刑事の訪問をうけ、その事件を調べると連続殺人の可能性があることを発見します。
ユニークなのは、犯罪事件で画期的な捜査手法となっているDNA検査の盲点や、それを民間企業が利用する場合に規制する法律などがなく、犯罪者にとっては利用価値のあるものというストーリー展開で、新鮮な切り口で楽しめました。
ハリー・ボッシュシリーズの中でも時々登場し、この小説でも大きな役割をする元FBI捜査官のレイチェル・ウォリングや、ハリー・ボッシュの元妻の元FBI捜査官だったエレノア・ウィッシュなど、主人公のロマンス相手として女性FBI捜査官を登場させるのが著者はお好きなようです。
★★☆
◇著者別読書感想(マイクル・コナリー)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
日本史の探偵手帳(文春文庫) 磯田道史
第1章 中世の武士と近世の武士の違い
第2章 歴史を動かす英才教育
第3章 古文書を旅する
第4章 歴史を読む
の4章にまとめたもので、2019年に文庫として出版されました。
歴史として定番と思っていたことや、時代劇映画などでよくあるシーンなどにも、歴史学者の目からはまた違った解釈や、あり得ない間違いと思うことがよくあるそうです、
例えば、ドラマなどでよくあるシーンとして、商人が、奉行や代官など役人に賄賂として金の小判を手渡すシーンがありますが、小判25枚を紙封した封金は、現在の価値に直すと750万円、菓子折の下に敷き詰めた小判は3億円にもなるそうで、そんな大金の賄賂をやりとりできるはずがないとか。
江戸時代の税金は基本が米で納める年貢だけなので、商売やその他で得られた収入には税金がかからないので、農民でも米以外の作物を作り、収入の道はいくらでもあったとか。一番貧乏なのは物入りも多い下級の侍という話など面白く読めます。
もっともそうした知識は、仕事の役にたったり、生きていく上で必要なモノではありませんが、日本の歴史の教養のひとつとして味わえます。
また最終章には、「日本と日本人を知る100冊」として著者お勧めの書籍があげられています。
★★☆
◇著者別読書感想(磯田道史)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
あなたならどうする(文春文庫) 井上荒野
歌謡曲のタイトルや歌詞からイメージを膨らませるというのは誰でも経験があるでしょうけど、小説家が創造するとちょっと変わった物語になります。
収録作はオリジナルの歌詞「人妻ブルース」、あとは短編小説で「時の過ぎゆくままに」、「小指の想い出」、「東京砂漠」、「ジョニィへの伝言」、「あなたならどうする」、「古い日記」、「歌いたいの」、「うそ」、「サルビアの花」です。
最初の「人妻ブルース」以外は、65歳以上の人は実際に耳にしたことのある昭和歌謡曲のタイトルです。
若い人には馴染みがないと思われるので、タイトルになった曲の歌手と発売年を書いておきます。
ほとんどが昭和40年代の曲です。
| 時の過ぎゆくままに | 沢田研二 | 1975年 |
| 小指の想い出 | 伊東ゆかり | 1967年 |
| 東京砂漠 | 内山田洋とクール・ファイブ | 1976年 |
| ジョニィへの伝言 | ペドロ&カプリシャス | 1973年 |
| あなたならどうする | いしだあゆみ | 1970年 |
| 古い日記 | 和田アキ子 | 1974年 |
| 歌いたいの | 山崎ハコ | 1975年 |
| うそ | 中条きよし | 1974年 |
| サルビアの花 | 早川義夫 | 1969年 |
短篇はそれぞれ歌詞をモチーフにしていますが、直接曲とは関係はなく、著者の創造力とイメージで書かれているようです。
「ジョニィへの伝言」などはわかりやすく、ジョニー大倉に似た彼氏と、二人でふるさとの町を出て行く予定だったのが、約束の時間になっても彼が来ず、ひとりで東京へ向かう主人公の話など。
一般的には小説中に歌詞を入れるのはJASRACへの使用料が発生するので出版社は嫌がりますが、そうしたことを超越して9作の歌詞が堂々と掲載されていて、編集者をきっと慌てさせたことでしょう。
こうして昭和時代の歌詞とそれをモチーフにしたドラマを並べると、その多くがベタベタした男と女の愛と別れの哀愁を歌い上げたものが多かったなぁという印象です。
もっとも数多くある中から著者自身がこれらの昭和歌謡を選んだわけなので、わざとそういう内容の歌詞を選んだとも言えますが、こういうモチーフの使い方、選び方は小説としては斬新で面白いです。
★★☆
◇著者別読書感想(井上荒野)
【関連リンク】
8月前半の読書 卑弥呼の葬祭、大名倒産、オーパーツ死を招く至宝、給食のおにいさん
7月後半の読書 ドリアン・グレイの肖像、悪い夏、東京自叙伝、ジヴェルニーの食卓
7月前半の読書 犬はどこだ、巡査長 真行寺弘道、罪責の神々 リンカーン弁護士、日本史を暴く 戦国の怪物から幕末の闇まで
| [PR] Amazonタイムセール/売れ筋ランキング | ||
Amazonタイムセール ホーム&キッチンの売れ筋ランキング 枕・抱き枕の売れ筋ランキング 旅行用品の売れ筋ランキング |
ミラーレス一眼の売れ筋ランキング 空気清浄機 タイムセール 掃除機の売れ筋ランキング ペット用品の売れ筋ランキング |
|
| [PR] Amazon 医薬品・指定医薬部外品 売れ筋ランキング | |||
鼻水・鼻炎 便秘改善 肌・皮膚トラブル改善 |
睡眠改善 関節痛・神経痛 肩こり・腰痛・筋肉痛 |
胃腸改善 整腸剤 喉・口中改善 |
目薬 育毛・養毛剤 痛み止め |
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
PR
1851
卑弥呼の葬祭 天照暗殺(新潮文庫) 高田崇史
単独と書きましたが、作中には以前事件を解決してくれたという「毒草師シリーズ」の主人公の名前が出てきたり、他の作品を全部読んだわけではないので不明ですが、完全に独立した作品かどうかは定かではありません。
テーマは、卑弥呼は誰か?ということですが、魏志倭人伝や記紀などから、国造りの神話、古代天皇など、様々に展開していき、多少はその辺りの知識がないと理解するのは結構大変です。
私は幸い、以前著者の「古事記異聞シリーズ」を読んでいて、国造り神話の解釈や登場人物について、ある程度の免疫ができていたので、さほど苦しむことなく面白く読めました。
舞台は、大分県の宇佐神社、宮崎県の高千穂周辺で、実際に存在する凶首塚古墳や百体神社、天岩戸神社など、いわくありげな地名や名称がいろいろと登場して読み応え十分です。
決して旅行ガイドブックではないですが、私は出雲地方へ旅行する前に「古事記異聞 鬼棲む国、出雲」を読んでおいてたいへん役立ちました。もし九州方面へ旅行する時には、一度読むことをお勧めしたい小説です。
★★☆
◇著者別読書感想(高田崇史)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
オーパーツ死を招く至宝(宝島文庫) 蒼井碧
タイトルの「オーパーツ」とは、「out of place artifacts」 の略で、発見された場所や時代とそぐわない遺物や加工品のことで、ひとことで言えば「場違いな工芸品」です。
例えば古代マヤ文明の遺跡から見つかったクリスタルスカルや、コロンビアの古代文明の遺跡から見つかった黄金のシャトル(飛行機)などが有名です。
この作品では、連作で4つの物語が収録されており、第1章「十三髑髏の謎」、第2章「浮遊」、第3章「恐竜に狙われた男」、第4章「ストーンヘンジの双子」とエピローグで構成されています。
第1章では、映画インディ・ジョーンズの「クリスタル・スカルの王国」で有名になったクリスタルスカル(水晶髑髏)、第2章では黄金シャトル、第3章では恐竜土偶、第4章ではストーンヘンジなどの石柱と、それぞれオーパーツがテーマとなっていて、そこに殺人事件が絡んできます。
主人公は、自称オーパーツ鑑定人の男子学生がホームズ役、顔がうり二つの同じ大学生がワトソン役として事件を解決していくというものです。
ミステリー小説としては、まだ荒削りというか、かなり設定に無理がありますが、日本人にはあまり馴染みがないオーパーツをテーマにした小説という珍しさがあり興味を惹かれます。
エピローグでは第4章に登場した謎の兄妹の双子について、続編を想像させる内容でしたが、今のところまだその続編は出ていないようです。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
大名倒産(上)(下)(文春文庫) 浅田次郎
3万石の越後の小藩では巨額の借金が積み重なり財政破綻が間近に迫っていたことから、藩主である先代が、町人の娘に手を出して産ませた人の良さそうな四男に家督を譲り、財政破綻の責任をすべて負わせ廃藩に追い込もうと画策します。
主人公はその悪だくみにはめられた長屋育ちの四男で、なにも知らされずに名門家の跡継ぎとなり、やがて自分が窮地に立っていることを知ることになります。
本作の舞台、丹生山(にぶやま)藩は越後の3万石を治める架空の藩ですが、立地的なモデルは江戸時代の村上藩(新潟県村上市)だそうです。
最初のうちは、真面目でシリアスな歴史小説と思いきや、途中から貧乏神やら七福神、疫病神、死神、薬師如来まで出てきて、てんやわんやの騒ぎです。
そう言えば著者の同じ江戸時代末期の時代小説に「憑神」という貧乏神が出てくる似たようなものが過去にありました。
そして文庫の解説の代わりに「浅田次郎×磯田道史」という対談が巻末に載っています。事実を追い求める歴史学者と、ほどほどに史実を散りばめて創造力を駆使しエンタメに仕上げる小説家が、それぞれの視点で歴史小説について対談をすることがとてもユニークで面白いです。
その対談は、文藝春秋のサイトでも読めます。
「対談 浅田次郎×磯田道史 改革をなし得る人とは」
小説と映画では登場人物に違いがあり、内容も少し変わっていそうですが、映画も見たくなりました。
★★★
◇著者別読書感想(浅田次郎)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
給食のおにいさん(幻冬舎文庫) 遠藤彩見
また本作品は単行本→文庫という通常の流れではなく、文庫書き下ろしです。
タイトルから想像していたとおりの展開で、仕方なく給食の調理員となった若い男性主人公が、その仕事や子供達との交流を通じて、今までの考え方をあらため、成長していくというストーリーです。
続編がすでに「給食のおにいさん 進級」(2014年)、「給食のおにいさん 卒業」(2014年)、「給食のおにいさん 受験」(2015年)、「給食のおにいさん 浪人」(2016年)と4作品が出版され、シリーズ化しています。
主人公はフレンチの名店で修行した経験があり、各種の料理コンテストで優勝した経験もある料理人で、独立して自分の店をオープンした直後に火事に見舞われ、しばらくどこかに勤めて貯金をしようと募集していた小学校の給食調理員になります。
様々な家庭環境の子供達や、給食という予算や栄養、子供達の好み、300人を超える大量の食事を短い時間で作るなど多くの制約がある中で、奮闘していきます。
私が小学生の頃(60年前)の給食と言えば、美味しいと思ったことは一度もなく、単にお腹を膨らませるためのもので、給食の時間が楽しみとか楽しいという感じはありませんでしたが、様々な報道などで知ってはいましたが今の給食は様変わりしています。
私の小学生の頃には主食は必ず食パンで、ご飯だったことは一度もなく、副菜もたいていは1品だけでした。
そして低学年の頃はまだ脱脂粉乳という飲むのさえ苦痛が伴うものが毎日出て、高学年の途中から牛乳に変わって救われた思いがありました。そして給食を全部食べるまで遊びには行けず、残すことは許されませんでした。
その様変わりした給食の内容を本著で詳しく知り驚きと共に、残しても良くなっているのは子供達の人権や、やかましい親に配慮した結果なのでしょう。
当初はよくあるお仕事小説かな?と思っていましたが、現代の給食事情や、モンスターペアレント、ネグレクトなど様々な社会問題をはらんだ社会派小説とも言えます。
★★☆
【関連リンク】
7月後半の読書 ドリアン・グレイの肖像、悪い夏、東京自叙伝、ジヴェルニーの食卓
7月前半の読書 犬はどこだ、巡査長 真行寺弘道、罪責の神々 リンカーン弁護士、日本史を暴く 戦国の怪物から幕末の闇まで
6月後半の読書 夜明けの雷鳴 医師高松凌雲、魂をなくした男、日本の地方政府、神座す山の物語
| [PR] Amazon 書籍 売れ筋ランキング | ||||
ビジネス・経済 ビジネス実用本 新書 文庫 文学・評論 コミック ゲーム攻略・ゲームブック |
ハヤカワ・ミステリー 創元推理文庫 新潮文庫 講談社文庫 角川文庫 集英社文庫 岩波文庫 |
文芸作品 ノンフィクション ミステリー・サスペンス SF・ホラー・ファンタジー 歴史・時代小説 経済・社会小説 趣味・実用 |
||
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
1849
ドリアン・グレイの肖像(新潮文庫) オスカー・ワイルド
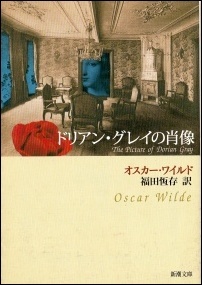 |
「ドリアン・グレイの肖像」(原題:The Picture of Dorian Gray)は、1990年に出版された長編小説で、友人から「日本の寺にある馬の絵から夜な夜な馬が飛び出し駆け回り、朝にはまた絵の中に戻ってくる」という話しを聞いたことがモチーフとなった(諸説あり)、肖像画にまつわる内容です。
主人公のドリアン・グレイは容姿端麗で美しい顔をした貴族の青年で、まだ少年だった頃に有名な画家のモデルをして、生き写しの肖像画ができあがります。
その肖像画を画家から贈られたドリアン・グレイは、やがて汚れた世間にまみれ老いて醜悪になっていく自分の姿とこの若さを失わない肖像画を比べ、思わず「自分がこの絵のように若さを失わず、老いていくのがこの絵だったら、どんな代償も惜しまない、魂だってくれてやる」と願掛けをします。
そうなるとおおよその展開がわかってきそうですが、主人公の青年が一目惚れで恋をし、つまらぬことで破綻し、また友人達が次々と悪の道へ落ちていき、最後は肖像画を描いてくれた友人の画家にまで手をかけることになっていきます。
著者はゲイ(当時は同性愛は犯罪)で逮捕されたことがあるそうですが、この小説にも同性愛を彷彿させるようなオブラートに包んだような表現がいくつもあります。当時はそれを具体的に書くだけで逮捕されるような時代だけに、歯がゆさが感じられます。
そういうストーリーながら、19世紀末頃の英国貴族社会の風潮はなにかと哲学的で難しく例えば、主人公と、その友人貴族の話しで、
| ドリアン、自己欺瞞はやめるのだ。人生は意志や意図で支配されているのではない。人生とは神経と繊維組織、そして徐々に形成される細胞の問題であり、これら神経や細胞の中に、想念が身を潜ませ、情熱が夢見るのだ。きみは自分を安全と信じ込み、強き人間と考えているのかもしれないが、しかし、部屋の中、あるいは朝空の中にふと認められた色あい、昔好きだったために、いまでも嗅ぐたびに妙なる思い出を匂わせる香水、かつて眼にふれたことのある忘れられた詩の一行、弾くことをやめてしまった曲の一節…いいかい、ドリアン、こういったものにこそ、人間の生活は左右されているのだ。 |
のようなよくわからないまどろっこしい言葉が多く紡がれていて、ライトノベルや大衆小説ばかりが馴染んでしまっている我が身には、こうした文学を読みこなすには結構な忍耐と想像が必要です。
そう考えれば、日本の文豪と呼ばれる人達、森鴎外や夏目漱石、谷崎潤一郎などが著者と著者の作品に大きな影響を受けたというのもわかります。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
悪い夏(角川文庫) 染井為人
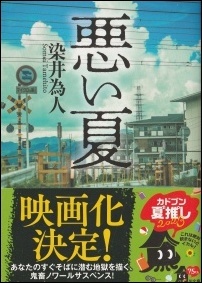 |
さらに今年2025年3月には城定秀夫監督、北村匠海、伊藤万理華、河合優実などの出演で、この小説を原作とした映画も公開されています。
生活保護制度やそれに関連した貧困ビジネスなどの社会問題については小説に取り上げられることも多く、私は柚月裕子著「パレートの誤算」や中山七里著「護られなかった者たちへ」を過去に読みました。
◇2023年4月後半の読書と感想、書評(パレートの誤算)
◇2024年5月前半の読書と感想、書評(護られなかった者たちへ)
生活保護を小説のテーマにすると、その内容は決して明るいものではなくなり、暗く重苦しいものとなってしまいます。
本著も貧困ビジネスや風俗、万引きなど犯罪のオンパレードで、「生活保護=闇と罪」というよくあるパターンで、読み進むにつれてページを繰るのがツラくなってきます。
しかし200万人と言われる生活保護受給者のうち、不正受給と思えるのは極めて特異な場合だと思います(そう信じたい)。
それだけにこうした特殊なケースの生活保護をテーマにした小説やそれを原作とした映画やドラマが制作されると、「生活保護=悪」という構図ができあがってしまい、それが本当に必要な人に抵抗感を与えてしまうことになりはしまいかと心配します。
役所側にとっては、少しでも申請を減らせる効果があり、加えて不正受給を思いとどまらせる効果があるのかも知れませんが。
小説はもちろんフィクションなので、なにをどう描こうとまったく自由です。そうしたことを考えれば、特殊なケースとは言え、エンタメとして読むべき事なんだろうなぁと思います。
あらすじは、地方都市の市役所勤務で福祉担当の独身男性、不正受給をしている中年男性、不正受給と受給額を増やしてもらう代わりに役所の担当者に身を提供しているシングルマザー、貧困ビジネスで安定したしのぎを画策しているヤクザなど、それぞれの視点で語られ、最後には一箇所にそれらの人達が一堂に会し大きな事件へと発展していきます。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
東京自叙伝(集英社文庫) 奥泉光
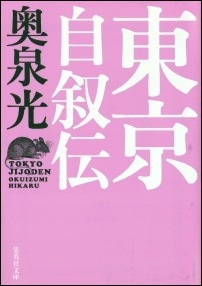 |
主人公である「東京の地霊の私」は次々と転移していきますが、記憶は縄文時代の頃からうっすらと残っていて、江戸時代には幕府の武士、昭和に入ってからは大本営の参謀、戦後には闇市にうごめくヤクザなど、次々と変わっていきます。
中盤辺りからは複数にまたがった「転移した私」の語りとなっていくことで、少々ややこしくなっていきます。
江戸や東京で起きた様々な出来事が出てきますが、それらは実際に起きた歴史をうまく利用しながら展開されます。
過去の別人の記憶が浮かび上がってきたり、ネズミが見たシーンかどうか不明だったりと、ややとっちらかった内容で、もう少しなにかに集中してまとめていった方が読みやすいだろうなと感じました。
首都東京をテーマにした小説は数々ありますが、その中でも個人的には1985年に出版された荒俣宏のSF小説「帝都物語」が一番深く刺さりました。
ただあれは映像化もされましたが、その時の映像はまだSFXが未熟な頃の作品で、イマイチ出来は良くなく、今の技術でリメイクされると良いのになぁと思ってしまいます。
★★☆
◇著者別読書感想(奥泉光)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
ジヴェルニーの食卓(集英社文庫) 原田マハ
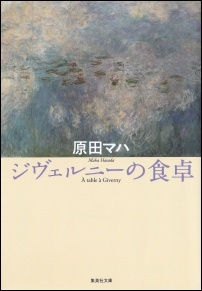 |
収録作品はそれぞれに印象派の巨匠と言われた著名な画家をテーマにした「うつくしい墓」、「エトワール」、「タンギー爺さん」、「ジヴェルニーの食卓」です。
「うつくしい墓」は、老女が若い時にアンリ・マティスの元で家政婦をしながら、パブロ・ピカソとの交流や、晩年の姿をル・フィガロの記者に語るという内容。
「エトワール」は、アメリカ人女流画家のメアリー・カサットが、友人だったエドガー・ドガの彫刻作品「14歳の小さな踊り子」のモデルについて、古い画商の仲間から問われるという話し。
「タンギー爺さん」は、パリで画材店兼画商をしていたタンギー爺さんと画家たちから呼ばれていた店主の娘が語り手で、セザンヌから出世払いにしていた借金を支払ってもらえるように督促する手紙や、他の貧乏な若い画家たちが、作品と交換に画材を買っていく話し、その中の若きフィンセント・ファン・ゴッホが店主をモデルにした肖像画を描いてプレゼントした話しなど。個人的にはこれが一番好きです。
最後の「ジヴェルニーの食卓」は、クロード・モネの義理の娘が語り手で、モネの苦悩と晩年の様子が描かれています。
しかし画家という職業、しかも突出した新しいスタイルを求める若い現役時代には批評家の意見は厳しく、評価も決まらず、貧困の中で苦しんでいるものだということがよくわかります。
個人的にはそうした西洋絵画や印象派の巨匠たちについて、名前と代表作以外はほとんど知らないので、こうした実在した画家たちの生々しい姿が身近に感じられる物語は読んでいて楽しいです。
著者の小説には、本著のように西洋美術の巨匠をテーマにした作品もあれば、まったく関係のない作品の両方がありますが、やはり圧倒的に前者の美術や画家をテーマにした小説の方が私にとっては興味を引かれて面白いです。
2年前に読んだ著者の作品「暗幕のゲルニカ」(2016年)はパブロ・ピカソとその愛人ドラ・マールがテーマでしたが、絵画のキュレーターとしても活躍する作家さんだけに、テーマの選び方や実際に起きた歴史を下敷きにした創作は素晴らしいのひと言です。
ちなみに、「暗幕のゲルニカ」は、「リス天管理人が2023年に読んだベスト書籍」の大賞を受賞しています。
★★★
◇著者別読書感想(原田マハ)
【関連リンク】
7月前半の読書 犬はどこだ、巡査長 真行寺弘道、罪責の神々 リンカーン弁護士、日本史を暴く 戦国の怪物から幕末の闇まで
6月後半の読書 夜明けの雷鳴 医師高松凌雲、魂をなくした男、日本の地方政府、神座す山の物語
6月前半の読書 果しなき流れの果に、センス・オブ・ワンダー、わくらば 短篇集モザイクIII、人新世の「資本論」
| [PR] Amazon 書籍 売れ筋ランキング | ||||
ビジネス・経済 ビジネス実用本 新書 文庫 文学・評論 コミック ゲーム攻略・ゲームブック |
ハヤカワ・ミステリー 創元推理文庫 新潮文庫 講談社文庫 角川文庫 集英社文庫 岩波文庫 |
文芸作品 ノンフィクション ミステリー・サスペンス SF・ホラー・ファンタジー 歴史・時代小説 経済・社会小説 趣味・実用 |
||
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
1847
犬はどこだ(創元推理文庫) 米澤穂信
個人的には探偵小説が好きで、タイトルからそれとわかる作品は好んで買いますが、さすがにこのタイトルで探偵小説という理解は及びませんでした。
主人公は有名な大学を出た後、都市銀行に入行しますが、肌が合わず病気になってしまい、都落ちで地元に帰ってきます。
病気療養という名の引きこもり生活をしていましたが、地元に戻ると病気はすっかり回復し、なにか自営業でもと思って「行方不明になった犬などペット探し」の調査会社、紺屋S&R(サーチ&レスキュー)を開設します。
しかし友人の紹介で訪ねてきた客はペットではなく人捜しや町の神社で見つかった古文書解読の仕事で、イヤイヤながらもそれに取り組むことになります。
都合良く、大学時代の後輩が出来高制で働いてくれたり、事務所開設直後に2件の依頼が入ったりと、まったく現実の厳しさは無視されていますが、軽薄で頼りなさそうな後輩が意外な活躍ぶりを見せたり、地元の喫茶店店主と結婚していた妹が意外な活躍をしたりと、ストーリー展開には激しい動きがあって面白く読めました。
そしてクライマックスでは、読者の多くが「あっ!」と驚く仕掛けが仕込まれています。さすがに一筋縄にはいかない作家さんです。
★★☆
◇著者別読書感想(米澤穂信)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
巡査長 真行寺弘道(中公文庫) 榎本憲男
本著は後に「巡査長 真行寺弘道シリーズ」となるシリーズ第1作目で、2018年に文庫として出版されました。
そういう意味ではまだ作家としては駆け出しの頃の作品と言うことになりますが、それを知らずに読んでいるとかなりベテランの作家さん?と思って読んでいました。
それほどストーリー展開や人物描写がうまく、460ページを超える長編ですが引き込まれてサクッと読めました。視点が主人公の一人称だけというハードボイルドのスタイルで、他の登場人物が限られ読みやすいということもあります。
ただ個人的には、小説や映画でよく使われるリアリティに欠ける安易な手法、つまり天才ハッカーが主人公に協力して様々な入手不可能なデータを不正入手したり、システムを書き換えたりするということが物語の重要ポイントになっていることが、どうにも安易で小説の質を下げてしまうことになり面白くありません。
巡査長とは警察の中でも最初に就く巡査の上の階級的職位で、実質はヒラの巡査と同じ階級にあたります。
主人公は50代で、刑事部長賞も得るなど事件解決では優秀な警視庁の刑事で、本来なら課長級の地位にいるのが普通ですが、自ら現場で好きなように捜査をしたいため昇級試験は受けずヒラに留まったままの変わり者の刑事です。
シリーズ作品としては、「ブルーロータス 巡査長 真行寺弘道」(2018年)など4作品がすでに既刊ですので、読んでみたいと思います。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
罪責の神々 リンカーン弁護士(上)(下)(講談社文庫) マイクル・コナリー
順序としてはこの後の作品の「潔白の法則 リンカーン弁護士」(米国2020年、日本語2022年)を先に読んでいます。
家族の問題や、過去に関連した人物がこの小説で再登場をしますが、ストーリーは続編的な展開ではないので、読む順番はあまり関係がありません。
もう一つの著者の代表作「ハリー・ボッシュシリーズ」は三人称で書かれますが、このシリーズは一人称です。それ故に登場人物が多くても視点がひとつなので読みやすいです。
今回の法廷劇は、娼婦が絞殺され、その娼婦のポン引き役の男が分け前のトラブルがあり逮捕されますが、その男が殺された娼婦からハラーのことを聞いていたことからハラーに弁護を依頼してきます。
娼婦のことを調べると過去に弁護をしたことがある女性で、娼婦の世界から足を洗わせたという自負があったものの、再び名前を変えて夜の世界に戻り殺されたことがわかります。
そこから話しがややこしくなりますが、娼婦がなぜ殺されたのか?という事情を調べていくうちに、様々な行動監視や妨害、意図的な事故が身に起き始めます。
また過去に殺された娼婦の弁護をしている時に、司法取引で麻薬を扱うメキシカンマフィアの大物を売ったことにも関係し、本来なら狙われるべき相手と手を組み、より大きな敵と対峙していくことになります。
ま、いつもと同じパターンで、終盤は痛快でテンポの良いリーガルサスペンスで、検事や相手側の証人をバッタバッタと斬っていくという次第です。
しかし、特に弁護士や検事などの経験はない作家(作家になる前は新聞記者)で、これだけの司法手続きや法律などに詳しいというのは驚くばかりです。
★★☆
◇著者別読書感想(マイクル・コナリー)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
日本史を暴く 戦国の怪物から幕末の闇まで(中公新書) 磯田道史
のたりくねった筆跡で書かれた戦国時代や江戸時代の古文書をスラスラと読んで、知識のない人にもわかりやすく解説してくれる能力と爽やかな弁説はテレビ向けでもあり各メディアはたいそう重宝しています。
私もNHK BSで放送されている「英雄たちの選択」は、毎週欠かさず録画して見ています。
第1章は「戦国の怪物たち」で織田信長や松永久秀、明智光秀、徳川家康などの裏話など、第2章は「江戸の殿様・庶民・猫」で、江戸時代の猫について書かれている古文書を探し出して紹介しています。
第3章は「幕末維新の光と闇」で、西郷隆盛、坂本龍馬、松平容保、伊藤博文などが登場し、チョンマゲのやめ方などもあります。
最後の第4章は、著者がもっとも力を入れている歴史から学び、災害を予見し、備える活動に準じた「疫病と災害の歴史に学ぶ」です。
「徳川家康が目指した社会」とか「本能寺の変が起きた理由は?」など、一般的な歴史の話しは、教養というのではなく雑学としての知識しか役に立ちそうもありませんが、疫病や災害について書かれた古文書や伝聞は現代でも大いに役立ちそうです。
★★☆
◇著者別読書感想(磯田道史)
【関連リンク】
6月後半の読書 夜明けの雷鳴 医師高松凌雲、魂をなくした男、日本の地方政府、神座す山の物語
6月前半の読書 果しなき流れの果に、センス・オブ・ワンダー、わくらば 短篇集モザイクIII、人新世の「資本論」
5月後半の読書 花の鎖、世界インフレの謎 そして、日本だけが直面する危機とは?、蝉かえる、氷の闇を越えて
| [PR] Amazon 書籍 売れ筋ランキング | ||||
ビジネス・経済 ビジネス実用本 新書 文庫 文学・評論 コミック ゲーム攻略・ゲームブック |
ハヤカワ・ミステリー 創元推理文庫 新潮文庫 講談社文庫 角川文庫 集英社文庫 岩波文庫 |
文芸作品 ノンフィクション ミステリー・サスペンス SF・ホラー・ファンタジー 歴史・時代小説 経済・社会小説 趣味・実用 |
||
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
1845
夜明けの雷鳴 医師高松凌雲(文春文庫) 吉村昭
主人公の高松凌雲は、福岡(筑後国)の農家出身で、その後養子に入り武士になりますが、医者を目指そうと江戸の親戚を頼って上京します。
頭が良く努力家で、当時広がり始めていた西洋医学の蘭学を学び、オランダ語や英語にも精通し、若くして時の将軍、徳川慶喜の奥詰医師へと出世します。
さらにフランスでおこなわれたパリ万博に渋沢栄一などとともに派遣が決まり、万博終了後も公費留学としてフランスで最新外科治療を学びます。そこで身分や貧富に関係なく医療が提供され、また貧しい者には無料で医療が受けられる制度に大きな衝撃を受けます。
ところが幕臣の身で留学をしていた時、日本では政変が起き、大政奉還があり、さらに鳥羽・伏見の戦いで逆賊とされた幕府が崩壊しつつあることを知り、急遽帰国することとなり、幕臣の立場から新政府軍と戦っている榎本武揚率いる幕府軍に合流して仙台、函館と流れていきます。
函館では、戦傷者を収容する函館病院をつくり、敵味方問わずに多くの治療をおこなっていきますが、幕府側の病院と言うことで追い詰められていきます。
結果的には、フランスでの留学中に感銘を受けた赤十字の思想を取り入れた病院経営思想を日本で始めておこなったことで有名になりますが、どれだけ求められても自分は幕府と将軍に育ててもらった恩があると、最後まで新政府側の役職には就かなかった信義の人でもあります。
医者から見た幕末の騒動は新鮮で、いつかは大河ドラマにも向いていそうな話です。
★★★
◇著者別読書感想(吉村昭)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
魂をなくした男(上)(下)(新潮文庫) ブライアン・フリーマントル
著者は昨年2024年12月に亡くなっているので、このシリーズはこれが最後ということになります。
前作、「顔をなくした男」は昨年読みましたが、ロシアでロシア人の妻子を英国へ亡命させるため、空港で作戦を実行中、支援チームで仲間のはずの英国のMI16情報員から銃撃され気を失い、気がついたときにはロシア連邦保安局(前身はKGB)に捕まっていたというところで終わりました。
その続きから始まりますが、どうやって最大の危機から逃れるか?という話です。
物語は、英国のMI5とMI6のトップを含めた危機管理委員会の会議室でおこなわれる応酬がメインで少々退屈です。よくある法廷ドラマのような感じです。
一般的にスパイ小説と言えば、スーパーマン的な主人公が、敵の裏をかいてスリル満点な活躍を描くものが多い中で、「事件は会議室で起きている」という内容です。
ただ、事件はその主人公の拘束だけではなく、ロシアの連邦保安局高官の英国への亡命や、前々作で出てきたロシア大統領候補に仕掛けられた謀略事件の後始末、さらに主人公の妻でロシアの保安局員の亡命も関わってきてかなり複雑に絡み合ってきます。
こうしたスパイものは欧米中心がほとんどですが、日本人として気になるのは、時々中国で日本人ビジネスマンが中国にスパイ容疑で拘束される事件が起きていることから、アジア地域を中心とするスパイ活動や謀略戦が知りたいところです。
日本ではどこでも写真を撮ることは問題ないですが、中国など一部の国では、カメラを向けただけで拘束される恐れがある地域や施設があり、平和ぼけ気味な日本人にはなかなか理解できないことです。
★★☆
◇著者別読書感想(ブライアン・フリーマントル)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
日本の地方政府(中公新書) 曽我謙悟
京都大学の教授として、また学者の論文風著書としてはしっかりしたものとなっているのですけど、とにかく話の内容が難しくはないけど固すぎて、小説でも読むような寝転がって読むようなものではありません。
タイトルの「地方政府」という言葉は聞き慣れませんが、一般的には地方自治体、または地方公共団体という言い方がされます。
昔は国の政府や政治家が決めたことをただ指示に従い実行するというスタイルが主流だったのに対し、何度かの地方分権などを経て、現在は権限が大幅に増えた権限を持った都道府県や市町村の政治が見直されてきています。
本著では、その1700を超える都道府県や市町村の地方政府にスポットをあて、政治制度や国との関係、地域社会について過去からの歴史を含めて書かれています。
国の行政とは違い、教育や警察、消防・救急、清掃など身近なことを決めるのが地方政府の役割でもあり、その仕組みや問題点などが参考になります。
また単なる市町村の合併だけではなく、本著では触れられていませんが、今後日本全体で急速に進む人口減少と経済縮小が続く中で、現在のあまりにも人口格差や経済格差がある都道府県のあり方や、エリアの見直しなども考えていく必要がありそうに思えます。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
神座す山の物語(双葉文庫) 浅田次郎
知りませんでしたが、著者の母親の実家が奥多摩にある御嶽山の歴史ある神官屋敷で、子供の頃には夏休みなどには帰省し、そこで様々な昔話を聞いたことからこの作品の創作のヒントになったようです。
収録作品は、「神上がりましし伯父」「兵隊宿」「天狗の嫁」「聖」「見知らぬ少年」「宵宮の客」「天井裏の春子」の7篇です。
語り手の実家の伯母が「子供の頃に本当にあったことなんだけどね」と、帰省で集まった子供達に寝物語を聞かせてくれるパターンで、巻末のロングインタビューで触れられていますが、柳田國男著「遠野物語」に触発されているのがわかります。
◇2013年8月後半の読書と感想、書評(遠野物語)
そして実体験や聞いた話の他、著者独自の創作ももちろん加わり、浅田ワールド全開の面白い内容となっています。
現在でも物語の舞台となっている「山香荘」は実在しています。時々滞在し、ここで生まれた作品も多いということです。熱心な浅田ファンはぜひ一度泊まりに行くべきでしょう。
作品の中で私が一番印象的だったのは最後の「天井裏の春子」で、キツネ憑きに遭った若い娘が母親に連れられ狐払いをしにやってくるという話です。
現在ではうつ病や解離性障害、統合失調症など精神系病気と診断されますが、戦前頃まではそうした科学的な治療はなく、もっぱら治療は神頼みというのが一般的でした。
憑いた老狐と神官とのやりとりなど、現代科学では理解しがたい昔話が面白く読めます。
★★★
◇著者別読書感想(浅田次郎)
【関連リンク】
6月前半の読書 果しなき流れの果に、センス・オブ・ワンダー、わくらば 短篇集モザイクIII、人新世の「資本論」
5月後半の読書 花の鎖、世界インフレの謎 そして、日本だけが直面する危機とは?、蝉かえる、氷の闇を越えて
5月前半の読書 月神、潔白の法則(上)(下)、歴史の愉しみ方 忍者・合戦・幕末史に学ぶ、怪物の木こり
| [PR] Amazon 書籍 売れ筋ランキング | ||||
ビジネス・経済 ビジネス実用本 新書 文庫 文学・評論 コミック ゲーム攻略・ゲームブック |
ハヤカワ・ミステリー 創元推理文庫 新潮文庫 講談社文庫 角川文庫 集英社文庫 岩波文庫 |
文芸作品 ノンフィクション ミステリー・サスペンス SF・ホラー・ファンタジー 歴史・時代小説 経済・社会小説 趣味・実用 |
||
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
|
カレンダー
|
|
最新記事
|
(01/24)
(01/17)
(01/10)
(01/03)
(12/27)
(12/20)
(12/13)
(12/06)
(11/29)
(11/22)
|
カテゴリー
|
|
ブログ内検索
|
|
最新コメント
|
[06/28 area]
[06/28 U・M]
[01/03 area]
[01/03 Anonymous]
[10/09 area]
|
プロフィール
|
HN:
area@リストラ天国
HP:
性別:
男性
趣味:
ドライブ・日帰り温泉
自己紹介:
|
過去人気記事
|
医者と作家の二刀流一覧
日本の農業はどこへ向かうか
ロバート・B・パーカー「スペンサーシリーズ」全巻まとめ
マイカーで東京から京都まで旅行する場合 その1
リタイア後の心配事
有効求人倍率がバブル時並みとは
スペンサーシリーズの読み方(初級者編)
年賀状と葬儀について
ガソリンスタンドのブランド変遷史
世界と日本の宗教別信者数
戦国武将たちの身長は?
証明写真機の種類と機能を調べてみた
ゴルフをプレイしている人の年代層割合に驚いた
活字離れは事実か?
サイコパスたちの宴
世界と日本の書籍ベストセラーランキング
変形性股関節症の人工股関節全置換手術
Amazon 売れ筋ランキング ドライブレコーダー レーダー探知機 空気清浄機 ペット用品 まくら・抱き枕 体脂肪計 スポーツウェア ランニングシューズ メンズスニーカー レディーススニーカー ゴルフクラブ ゴルフシューズ ミラーレス一眼カメラ ゲーム ノートパソコン プリンタ イヤホン・ヘッドホン スマートフォン スマートウォッチ microSDカード 防犯カメラ スペシャリティアパレル ラーメン レトルト・料理の素 シャンプー・コンディショナ スキンケア・ボディケア |
