|
リストラ天国 ~失業・解雇から身を守りましょう~
HomePage https://restrer.sakura.ne.jp/
|
1875
マーチ博士の四人の息子(ハヤカワ文庫) ブリジット・オペール
推理サスペンス小説ですが、ホラーの要素もありなかなか楽しめます。
主人公は、アメリカの裕福な家でメイドとして働いている独身の女性で、過去に犯罪で刑務所に収監された経験があり、現在も別の犯罪で警察に追われているという感情移入ができそうもない人物です。
その主人公が働く家には、医者の主人、その妻、4人の子供(4つ子)が住んでいますが、その子供のひとりが書いたと思われる日記を偶然見つけ、それを読むと、過去に何人もの殺人を犯し、今後も次のターゲットが書かれています。そしてそのターゲットとされた女性が殺されたり、事故に見せかけて亡くなったりします。
その殺人犯の日記と、メイドの日記がずっと繰り返され、やがてはお互いの存在が判明し、やりとりをするようになりますが、その殺人犯が4人の子供のうち誰なのかはずっとわかりません。
この双方の日記でのやりとりが長く、ダラダラと延々と続くのが結構つらく、読み飛ばさずにはいられません。
こういう小説なので、単純に4人の息子のうちの誰かが犯人だったというオチにはならないと思っていて、あれこれ自分で想像してみましたが、突拍子もないエピローグで、いずれも外れてしまいました。
そりゃそうです、一度も登場してこない人物が犯人なんてそれは反則技でしょう。
それにしても、最終的に事件が解決する要因が、主人公が刑務所に入っていた時の習慣の「あること」からというのは秀逸でした。
★☆☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
美食探偵(角川文庫) 火坂雅志
その中でも珍しい明治時代を背景にした探偵小説で、2000年に単行本、2003年に文庫化された長編小説です。
主人公は、報知新聞社の編集長で、またグルメ情報「食道楽」などを書いている作家にして、謎を解き明かす素人探偵です。
連作短篇集形式になっていて、「海から来た女」、「薄荷(はっか)屋敷」、「消えた大隈」、「冬の鶉(うずら)」、「滄浪閣(そうろうかく)異聞」の5篇が収録されています。
それぞれの短篇は、明治時代に実在していた建物が舞台となっていて、「大磯の禱龍館(とうりゅうかん)」、「横浜のグランドホテル」、「築地メトロポールホテル」、「箱根離宮」、「伊藤博文邸、滄浪閣」が登場し、親切にも当時の写真が掲載されています。
余談ですが、それらの中で唯一知っていそうなグランドホテルは横浜にあるクラシックホテル、ニューグランドが名前を変えたそれかなと思っていましたが。グランドホテルは1923年(大正12年)の関東大震災で倒壊したため廃業していました。ただその同じ場所に別の法人が外国人向けの高級ホテルとしてニューグランドを建てたということです。
こうした学校では習わない明治時代の話しは、内容はフィクションとは言え、その中に事実も散りばめられたこうした小説で知ることが多く、雑学ですがたいへん面白く興味がわきます。
★★★
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
嵐が丘(角川文庫) E・ブロンテ
Heights(ハイツ)は、日本では場所は問わずチープな集合住宅の名称によく使われていますが、本来は、丘など高台にある大きな一軒家の屋敷に付けられる名称で、本著では主人公達が住む屋敷がワザリング・ハイツ(意訳:嵐が丘)と呼ばれています。
作品は1847年(日本では江戸時代)に最初に出版された長編小説で、著者のエミリー・ブロンテは、1818年イギリスのヨークシャー生まれで、28歳で本作品を刊行後、わずか1年経った1848年に病死します。本作品が高く評価されるようになったのは著者の死後のことです。
「リア王」「白鯨」とともに、英米文学では三大悲劇とされています。また1939年から今年2026年まで8回映画化されています。その中の1992年公開の映画では坂本龍一が音楽を担当しています。
英国の田舎町にある大地主が住む二つの大きな屋敷があり、そこが主な舞台となります。その屋敷のひとつはいつも強風にあおられていて、Wuthering Heights(嵐が丘)と呼ばれています。
物語はその屋敷に住む家族3代にわたる大叙事詩で、180年前に書かれただけに、現代の感覚からすると相当時代を感じます。180年前と言えば、日本は江戸後期で、まだペリー来航の前で、鎖国中でした。
内容は、恋愛などもありますが、その多くは差別や裏切り、病気、謀略など暗くて重い話しが多く、最後には少し救われますが、悲劇だけに読み進めていくのが結構つらく重苦しいです。
そして子供の頃に孤児だったのを救ってもらい育ててもらったにも関わらず、恨みを持ち、恩知らずの性格破綻している嫌なヤツ(主人公のひとり)を中心に物語は回っていくので、出版当初は評価が低かった理由もわかります。
この小説が最初に邦訳版で出版されたのは昭和32年(1957年)で、今回読んだ文庫改訳版の初版は昭和38年(1963年)版(平成8年改版41版)です。
したがって昭和38年当時の言葉遣いがそのまま残されていて、現代では差別用語として使われない言葉「きちがい」「こじき」「つんぼ」が何度も出てきたり、裕福な地主の若い娘さんが「よござんす」とか、英国のお嬢様が着るドレスのことを「着物」という翻訳にちょっと目が点になってしまいます。
増版するときに、出版社は訳者の許可(翻訳者は亡くなってますのでその権利継承者)は必要でしょうけど、どうして現代風に最低限の修正をしないのか不思議です。他の新潮社版や講談社版などではもう少し現代風の訳になっているのでしょう。
それにしても、英国の3世代にわたる大河小説で、久々に何冊かに及ぶような大作を読んだ気分になりました(この角川文庫は本文500ページ)。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
こちら横浜市港湾局みなと振興課です(文春文庫) 真保裕一
タイトルから著者の過去の作品にも多くある公務員を主人公にした「お仕事小説」?と思って読みましたが、それに間違いはありませんでした。
実際の横浜市には港湾局はありますが、「みなと振興課」という部署はありませんが、似た「賑わい振興課」というのがあります。それがモデルなのか不明ですが、創作なのでしょう。
主人公は横浜市の港湾局に勤めるヒラの事務職女性と、新たに配属されてやってきた国立大卒のエリート男性の2名で、仕事に絡む中で問題が発生しますが、その不思議な謎の原因を突き止め、穏便に済ませ表面化しないように苦心します。
また本来なら横浜市の局の中でも出世コースではない港湾局に国立大卒エリートが配属された謎(事実かどうかは不明であくまでフィクションです)についても徐々に明らかとなっていきます。
やがて戦前に外国人が多く住み商売などをおこなっていた横浜の歴史や、シアトルへの定期航路で活躍していた氷川丸についてなど、様々な横浜の一面が見られて面白かったです。
そう言えば、先日読んだ火坂雅志著の「美食探偵」も舞台となった時代は違いますが、横浜や大磯などの歴史がテーマとなっていて、意図していませんが、なぜか続きます。
★★☆
◇著者別読書感想(真保裕一)
【関連リンク】
1月前半の読書 貴族探偵、ナオミとカナコ、日本のこころ、阿修羅のごとく
12月後半の読書 「司馬遼太郎」で学ぶ日本史、容疑者、教会堂の殺人、その先の道消える
12月前半の読書 帰還、探偵の流儀、眠り姫(上)(下)
| [PR] Amazon 書籍 売れ筋ランキング | ||||
ビジネス・経済 ビジネス実用本 新書 文庫 文学・評論 コミック ゲーム攻略・ゲームブック |
ハヤカワ・ミステリー 創元推理文庫 新潮文庫 講談社文庫 角川文庫 集英社文庫 岩波文庫 |
文芸作品 ノンフィクション ミステリー・サスペンス SF・ホラー・ファンタジー 歴史・時代小説 経済・社会小説 趣味・実用 |
||
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
PR
1874
2012年から続けている毎年恒例のリス天管理人が独断で選ぶ年間BEST書籍大賞の発表です。パチパチパチ
選考についてあらためて書いておくと、管理人が2025年の1年間に読んだ書籍の中から選びますが、読む書籍のほとんどは諸般の都合上、何年も前に発刊された古いものが多く、新刊本はほぼ入っていません。
ジャンルは、新書やビジネス、エッセイ、ノンフィクションなどの部門(以下「新書」でくくってます)、海外小説部門、国内小説部門の3つに分けてそれぞれ大賞を選びます。
2025年は作品数で97作品、冊数では109冊を読みました。1作品で上巻、下巻等に分かれているものがあるので冊数は増えます。
| 新書/ノン フィクション |
冊数 | 海外小説 | 冊数 | 日本小説 | 冊数 | 作品数 | 冊数 | 月間平 均冊数 |
|
| 2013年 | 86 | 98 | 8.2 | ||||||
| 2014年 | 26 | 26 | 13 | 17 | 62 | 70 | 101 | 101 | 8.4 |
| 2015年 | 17 | 17 | 12 | 65 | 94 | 107 | 8.9 | ||
| 2016年 | 14 | 14 | 12 | 16 | 65 | 79 | 91 | 109 | 9.1 |
| 2017年 | 26 | 26 | 16 | 21 | 62 | 70 | 104 | 117 | 9.8 |
| 2018年 | 26 | 26 | 9 | 13 | 64 | 71 | 99 | 110 | 9.2 |
| 2019年 | 29 | 29 | 8 | 9 | 71 | 77 | 108 | 115 | 9.6 |
| 2020年 | 29 | 30 | 14 | 19 | 51 | 56 | 94 | 105 | 8.8 |
| 2021年 | 22 | 22 | 13 | 21 | 58 | 69 | 93 | 112 | 9.3 |
| 2022年 | 11 | 11 | 15 | 16 | 73 | 80 | 99 | 107 | 8.9 |
| 2023年 | 16 | 16 | 17 | 27 | 63 | 67 | 96 | 110 | 9.2 |
| 2024年 | 24 | 24 | 14 | 17 | 58 | 60 | 96 | 101 | 8.4 |
| 2025年 | 23 | 23 | 17 | 24 | 57 | 62 | 97 | 109 | 9.1 |
前年の2024年と比較すると、作品数で1作品、冊数では8冊増えました。年々視力と集中力が弱ってきていますが、なんとかこの趣味は順調に推移しています。
ジャンル別では、新書などはマイナス1作品(冊)、海外小説はプラス3作品、7冊、国内小説はマイナス1作品、プラス3冊という結果で、海外小説がやや増えましたが、全体的には昨年と似ています。
◇ ◇ ◇
それではいよいよ各ジャンルの大賞の発表です!
まずは新書、ビジネス、エッセイ、ノンフィクション部門です。
読んだ作品数は23作品(23冊)で、その中から候補作としては、
・夜明けの雷鳴 医師高松凌雲 吉村昭
・歴史の愉しみ方 忍者・合戦・幕末史に学ぶ 磯田道史
・サイコパス 中野信子
・いつかの夏 名古屋闇サイト殺人事件 大崎善生
・たのしい知識 ぼくらの天皇(憲法)・汝の隣人・コロナの時代 高橋源一郎
この5作から、、、
夜明けの雷鳴 医師高松凌雲(文春文庫) 吉村昭著 に決定です!
「6月後半の読書と感想、書評(夜明けの雷鳴 医師高松凌雲)」
あまり有名ではありませんが(この本を読むまで知りませんでした)、幕末の動乱時期から明治にかけて、実在した医師、高松凌雲を描いた歴史小説です。
徳川慶喜の奥詰医師を務めていたことから戊辰戦争では旧幕府軍に合流し、箱館戦争の時には敵味方問わず戦傷者を収容する病院を作りその後赤十字の元となる組織を作った人です。
2025年は歴史学者の磯田道史氏の新書を5冊読みました。いずれも面白く読めましたが、今回は惜しくも大賞には及びませんでした。2020年には「無私の日本人」で大賞に輝いています。
また、中野信子著「サイコパス」は、世界の特異なリーダー達の行動や考え方を理解するのに大いに役立ちます。
それを元ネタにしたブログも書いています。
◇サイコパスたちの宴 2025/11/22(土)
そういうリーダーばかりが跋扈してきた世界がこれからどうなっていくかは不安でしかありませんが、きっとそのうち大きな揺り戻しがやってくることをジッと待つしかないのでしょう。
◇ ◇ ◇
次に海外小説部門です。2025年は17作品、24冊の海外小説を読んでいます。
なぜか海外小説は上下巻に分かれている長編が多いです。1作品当たりの値段を上げるための出版社の作戦かも知れません。
今回の海外小説には、高評価とする★3が17作中5作(29%)もありました。こうした高評価の割合が高いのは珍しいです。
・潔白の法則(上)(下) マイクル・コナリー
・高慢と偏見(上)(下) ジェイン・オースティン
・続高慢と偏見 エマ・テナント
・メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ
・十五少年漂流記 ヴェルヌ
1813年に出版された「高慢と偏見」や、1888年に出版された「十五少年漂流記」もあり、2020年に出版された「潔白の法則」までかなり年代的には幅広い選択ですが、この5作品はいずれもお勧めできる作品です。
これらの候補の中で、どうしても甲乙付け難く、特別に2作を大賞とします。
大賞は、
高慢と偏見(上)(下)(ちくま文庫) ジェイン・オースティン著
メインテーマは殺人(創元推理文庫) アンソニー・ホロヴィッツ著
まぁ、過去の評価や評判からすれば、無難な選考と言われるとその通りですが、選ぶ側(私)もいたって凡人なので、仕方がないのです。
感想は、
3月後半の読書と感想、書評(高慢と偏見)
4月後半の読書と感想、書評(メインテーマは殺人)
感想は上記リンク先を読んでいただくとして、両方とも結構ボリュームがあり、さらに登場人物が多くて慣れるまでは苦労します。
しかし中程ぐらいまでくると、あとは要領がわかり、面白くなってきてスイスイと読めますので、前半は我慢して理解しながらじっくり読み進めることをお勧めします。
「十五少年漂流記」は小学生だった頃にところどころに絵が入った簡易な児童書版を読んだ記憶がありますが、内容はすっかり忘れていて、今回ちゃんとした小説を読んであらためてその内容がよくわかりました。
無人島小説は好きでよく読みますが、これはリアリティさはなく、やっぱり児童向けのおとぎ話だなと思います。
◇ ◇ ◇
最後は読書数としてはもっとも多い日本の小説部門です。57作品、62冊読みましたが、高評価★3が点いた作品は10作品(18%)ありました。
海外小説の29%には及びませんが、これも比較的高評価な作品の割合が多かったなという印象です。最近評価が甘くなってきたのかも知れません。
その中でもさらに高評価な作品を選んだ大賞候補作は、
・世界でいちばん透きとおった物語 杉井光
・ジヴェルニーの食卓 原田マハ
・果しなき流れの果に 小松左京
・罪の轍 奥田英朗
・何もかも憂鬱な夜に 中村文則
の5作品です。
超絶技法の小説「世界でいちばん透きとおった物語」(2023年)、印象派の誕生と著者独特の感性が生きる「ジヴェルニーの食卓」(2013年)、SF小説の古典的名作「果しなき流れの果に」(1966年)、一級品のクライムサスペンス「罪の轍」(2019年)、死刑制度への問題を突きつける「何もかも憂鬱な夜に」(2009年)と、世に出た時期はそれぞれ違いますがいずれも読み応えのある秀作です。
その中から、大賞に選んだのは、、、、、
ドコドコドコドコドコ、パァーン!
ジヴェルニーの食卓(集英社文庫) 原田マハ著に決定です!!
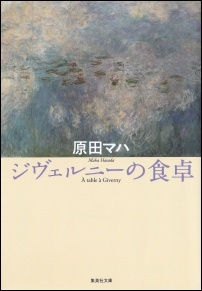 |
感想は、
7月後半の読書と感想、書評(ジヴェルニーの食卓)
同様に西洋画の巨匠をテーマにした小説「楽園のカンヴァス」や「暗幕のゲルニカ」も良かったですが、今回の短篇集では印象派の巨匠となる画家達の若く貧しい中で必死に生きる姿が生き生きと描かれています。
西洋画に詳しくない人(私)でもわかりやすく、画家達への興味が次々とわいて湧き出してきます。
そして惜しくも次点となった作品、「罪の轍」(2019年)奥田英朗著を特別賞としておきます。
感想は、
2月前半の読書と感想、書評(罪の轍)
親からの虐待を受け、超絶貧困状態で、仲間と思っていた仕事仲間に罪を着せられ、北海道の離島から逃げ出した精神的に不安定な男の物語です。
昨年は、海外小説と国内小説の両方で私にとって多くの名作と出会うことができました。
今年も多くの名作に出会えることを願ってやみません。あー楽しみだ。
【過去のベスト書籍】
1824 リス天管理人が2024年に読んだベスト書籍
1767 リス天管理人が2023年に読んだベスト書籍
1692 リス天管理人が2022年に読んだベスト書籍
1601 リス天管理人が2021年に読んだベスト書籍
1500 リス天管理人が2020年に読んだベスト書籍
| [PR] Amazon 書籍 売れ筋ランキング | ||||
ビジネス・経済 ビジネス実用本 新書 文庫 文学・評論 コミック ゲーム攻略・ゲームブック |
ハヤカワ・ミステリー 創元推理文庫 新潮文庫 講談社文庫 角川文庫 集英社文庫 岩波文庫 |
文芸作品 ノンフィクション ミステリー・サスペンス SF・ホラー・ファンタジー 歴史・時代小説 経済・社会小説 趣味・実用 |
||
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
1873
貴族探偵(集英社文庫) 麻耶雄嵩
収録作は、「ウィーンの森の物語」「トリッチ・トラッチ・ポルカ」「こうもり」「加速度円舞曲」「春の声」 の5篇で、いずれも単独の殺人事件です。
よくわからないですが、なんでも「やんごとなき」貴族の探偵(名刺にも貴族探偵という記載しかない)が殺人事件現場に居合わせ、警察の上から圧力をかけて、現場の捜査に加わり、貴族探偵の使用人達(執事やメイド、自家用車の運転手)が、推理し、犯人を名指しして事件解決に至るというものです。
ちなみに日本ではすでに皇族を除いて貴族や華族という制度はなくなっていますので、あえて貴族というのは皇族ということなのでしょう。
主人公の貴族探偵自身は、「そういうつまらないことは雇っている使用人の仕事」とばかりに、関係者の聞き取りや事件現場の検証などには一切加わりません。
探偵小説の中には、アガサ・クリスティ著の「ミス・マープルシリーズ」のような、自身で調査などはおこなわず、状況を誰かに聞いただけで推理をし、事件を解決する「安楽椅子探偵」というジャンルがありますが、本作の場合は、事件を解決するのは貴族探偵と名乗っている本人ではなく、その探偵の使用人達で、それとも違っていて笑えます。
そうした背景はともかく、事件のトリックについては、それぞれなかなか凝っていて、謎解き探偵小説として十分に楽しめるものでした。
★★☆
◇著者別読書感想(麻耶雄崇)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
ナオミとカナコ(幻冬舎文庫) 奥田英朗
2016年にはフジテレビが同名タイトルでテレビドラマを製作しています。主演の二人は広末涼子と内田有紀で、いかにも心の奥底に闇を抱えた女性という感じです。
内容は、夫からDV被害を受けている女性と、その親友の女性が夫の殺害計画を立て実行します。勤め先の金を横領して失踪したように見せかけますが、そこは素人の犯罪で、様々なミスが後になってから露わになっていきます。
犯行に至るまで、犯行時、犯行後の二人の主人公の心理描写がとにかく重苦しくて、気楽に読むにはつらすぎます。精神的に健全なときに読むことをお勧めします。
著者の小説には直木賞に輝いた「空中ブランコ」(2004年)のようなコミカルなライトなものもあれば、「オリンピックの身代金」(2008年)や「罪の轍」(2019年)のような重苦しいクライムサスペンス小説の2種類があり、この小説は後者になります。
果たして犯罪に手を染めた二人の女性は逃げ切ることができるのか?というストーリーですが、その展開にドキドキさせられます。
★★☆
◇著者別読書感想(奥田英朗)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
日本のこころ(文春文庫) 平岩弓枝
著書の中でも有名なのは、1959年、27歳の時に直木賞を受賞した「鏨師(タガネシ)」や、NHKの朝ドラの原作にもなった「旅路」、30年以上続く「御宿かわせみシリーズ」、テレビドラマになった「肝っ玉かあさんシリーズ」などです。またエッセイも多く残っています。
本著はそのエッセイの中でも最晩年の2019年から2021年頃に「オール讀物」に書かれたものと、1974年に神田明神でおこなわれた講演会から抜粋したもので構成され、亡くなった後の2024年に文庫本として発刊されています。
エッセイの中には、直木賞を受賞する前の駆け出しの頃から、受賞後に怖くて仕事を断ることができずかなり無理をして書きまくった話し、生まれが渋谷区の代々木八幡という神社のひとり娘で、戦争中には疎開したり、近所に友達がいなくて犬を飼ってもらったりしていた子供の頃の話し、文学の師匠、長谷川伸氏に師事した経緯や、そこで先輩の伊東昌輝と知り合って結婚した話しなど興味深く読めました。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
阿修羅のごとく(文春文庫) 向田邦子
著者の小説は、やはりNHKドラマの脚本から著者自身で小説化した「あ・うん」を23年前に読んで以来です。
テレビドラマは、八千草薫、いしだあゆみ、風吹ジュン、加藤治子などの出演で、NHKの土曜ドラマとして4回放送されました。八千草薫48歳、風吹ジュン27歳の頃のドラマです。
その後2003年には森田芳光監督、大竹しのぶ、黒木瞳、深津絵里、深田恭子などの出演で映画化されています。
上に書いたそれぞれ4人の出演者はいずれも主人公の四姉妹役で、この四姉妹の両親、夫、恋人、愛人などが複雑に絡み合いながら人間の愛憎を描いています。
さらに、Netflixで2025年に是枝裕和監督、宮沢りえ、尾野真千子、蒼井優、広瀬すずの出演で連続ドラマが作られています。時代が変わっても、人間の愛憎劇は変わりがないということです。
それにしても、テレビ向けに極端な脚色がしてあり、四姉妹とも心の奥に闇があり、あちらこちらに、妬みや嫉妬、愛人や不倫などてんこ盛りで、世の中の満たされない女性達にきっとウケたことでしょう。
それに対して、登場する男性陣は、いずれも寡黙だったり、気弱で引っ込み思案だったりしてまったく精彩がありません。
その数少ない男性役として、1979年のドラマでは気弱な性格ながら興信所の探偵で、その後、四姉妹の中ではもっとも貞操観念が強い三女の恋人役に、すでにダウン・タウン・ブギウギ・バンドで活躍中の当時33歳の宇崎竜童が出ているのが興味あるところですが、私は見ていません。
★★☆
【関連リンク】
12月後半の読書 「司馬遼太郎」で学ぶ日本史、容疑者、教会堂の殺人、その先の道消える
12月前半の読書 帰還、探偵の流儀、眠り姫(上)(下)
11月後半の読書 クロイドン発12時30分、流人道中記、2035年の世界地図、歴史とは靴である
| [PR] Amazon 書籍 売れ筋ランキング | ||||
ビジネス・経済 ビジネス実用本 新書 文庫 文学・評論 コミック ゲーム攻略・ゲームブック |
ハヤカワ・ミステリー 創元推理文庫 新潮文庫 講談社文庫 角川文庫 集英社文庫 岩波文庫 |
文芸作品 ノンフィクション ミステリー・サスペンス SF・ホラー・ファンタジー 歴史・時代小説 経済・社会小説 趣味・実用 |
||
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
1871
あけましておめでとうございます。
今年もつまらない話しや感想を書いていくつもりですので、よろしくお願いいたします。
稀少で物好きで変態な読者の方々には感謝しかありません。
ある日、ぷっつりと更新が途絶えた時は、管理人がとうとう逝ったかと思ってくださって結構です。
それでは今年の最初は恒例の読書感想からです。
◇「司馬遼太郎」で学ぶ日本史(NHK出版新書) 磯田道史
◇容疑者(創元推理文庫) ロバート・クレイス
◇教会堂の殺人(講談社文庫) 周木律
◇その先の道に消える(朝日文庫) 中村文則
◇ ◇ ◇
「司馬遼太郎」で学ぶ日本史(NHK出版新書) 磯田道史
司馬遼太郎作品は多岐に渡っていますが、その中でも日本が大きく動いた「戦国時代」、「幕末」、「太平洋戦争以前」の3つの時代が中心となっています。
とりあげられる主な作品は、「戦国時代」は「国盗り物語」(1965-1966年)、「幕末」は「龍馬がゆく」(1963-1966年)や「花神」(1972年)、「太平洋戦争以前」は「坂の上の雲」(1969-1972年)が主に紹介されています。
また「この国のかたち」(1990年-1996年)などのエッセイからも司馬氏の強いメッセージを紹介しています。
通常は歴史学者が、歴史文学(時代小説)について、あれこれ評論したり評価をすることはありません。歴史家は様々な資料を読み解き、史実を追究することが第一義で、小説は読み手が楽しめるような創意工夫をして創作します。
そうした同じ歴史でも目的がまったく違い相容れないところがあるので、こうした歴史学者が小説や歴史小説作家について語るのは珍しいです。
もっとも若手学者が、国民のほとんどが知る歴史小説の大家を語るわけですから大いに持ち上げていて、その真の狙いや思惑を好意的に解釈しています。
私自身は、以前は歴史小説があまり好きではなかったこともあり、司馬遼太郎氏の小説はあまり多くは読んでなく、長編大作を読むのはちょっと厳しいかも知れませんが、もう少し読んでみようと思う内容でした。
★★☆
◇著者別読書感想(磯田道史)
◇著者別読書感想(司馬遼太郎)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
容疑者(創元推理文庫) ロバート・クレイス
本著は上記の私立探偵が主人公のシリーズ作品ではなく、警官とその相棒となる警察犬が主人公で、原題は「Suspect」、出版は2013年(日本語翻訳版は2014年刊)です。
この作品がシリーズ「ロス市警警察犬隊スコット・ジェイムズ&マギー」の第1作目となり、2作目の「約束」(2017年)がすでに出版されています。
パトロール中に襲撃事件に遭遇し、パートナーだった女性警官が死亡、自身も重傷を負った主人公と、アフガニスタンで軍事作戦中にパートナーの兵士を目の前で射殺され自身も傷ついた軍用犬シェパードのマギーという同じようなトラウマを抱える同士、新たなコンビを組むことになります。
今回は、その警邏中に襲撃されて死亡した民間人2名と警官1名の事件を調べる中で、不可解な点が見つかり、様々な妨害に遭いながら、相棒の警察犬とともに事件の解決へ向けて真実に迫っていくという内容です。
パートナーが犬という小説や、犬が大きな役割を果たす小説はいくつもありますが、印象に残っているのは柴田哲孝著の「私立探偵・神山健介シリーズ」で出てくる、主人公の相棒のカイです。
またディーン・R. クーンツも犬の好きな作家で、ちょっと古いですが「ウォッチャーズ」(1987年)、「何ものも恐れるな」(1998年)など、犬が相棒役というか準主役として出てきます。
「私立探偵エルヴィス・コール&ジョー・パイクシリーズ」は、私が好きで全巻読み終えているロバート・B・パーカーの「スペンサーシリーズ」と似ていることから今後読んでいこうと思います。
★★☆
◇著者別読書感想(ロバート・クレイス)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
教会堂の殺人(講談社文庫) 周木律
本作品は、デビュー作から続く、通称「堂シリーズ」と言われている「○○堂の殺人」の5作目で、2015年に単行本、2018年に文庫化されています。
登場人物など共通することから第1作から順に読むのが正しい読み方ですが、途中から読むことになってしまいました。ま、こういうことはよくあります。
ちなみに、デビュー作でシリーズ1作目の「眼球堂の殺人」も購入済みですので、前後しますがそのうち読むつもりです。
内容は、続きものではなく、1話完結のミステリー小説ですので、登場人物の背景などは想像するしかありませんが、特に問題はなく最後まで楽しめました。
ただ、ストーリーにかなり突拍子もない無理なところがあったり、「それはないだろう」と思うところがあり、そうした細かなところは気にせず、おおらかに単純に楽しみながら読むのが良さそうです。
この「堂シリーズ」は著者が大学時代に建築を学んでいたことから、奇想天外な構造物(≒堂)が登場し、そこで殺人事件が発生するというお約束になっているようです。
と言うと、思い出すのが、綾辻行人著の「十角館の殺人」など一連の「館シリーズ」を思い浮かべますが、建物がミステリーやホラーの肝になっている小説は数多くあります。
この「堂シリーズ」は、2019年刊の7作目の「大聖堂の殺人」で終了となったようです。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
その先の道に消える(朝日文庫) 中村文則
たまたま1年半前に読んだ「あなたが消えた夜に」はベテラン刑事と新米のエリート女性刑事のコンビという警察小説でしたので、警察ものは今回が2作品目ということになります。
第1部と第2部に分かれていて、第1部と第2部で主人公というか語り手が違います。
あまり縁がなかったというかほとんどの人には縁がないでしょうけど、緊縛師というか女性を縄で縛るという極端なSM趣味の話が展開されていきます。
緊縛やSMと言えば唯一知っているのは「花と蛇」の作者、団鬼六氏の名前ですが、団氏は作家やプロデューサーであって緊縛師ではないのですね。調べてわかりました。
緊縛は海外ではアーチストという位置づけですが、日本ではその成り立ちや江戸時代の浮世絵からしてなにか陰湿で特殊なエロチックな趣味の世界みたいな印象です。
、
そうした緊縛師のひとりが殺され、捜査していた刑事が、その深遠な世界にはまっていくことになります。
第2部ではトラウマを抱えた別の刑事が謎解きをしていくという流れです。
非日常が味わえますが、どうにもそうした趣味の世界が理解しがたい凡人なので、どうしてそうなるの?という疑問だらけになってしまいました。
またこの作品に限らず、警察もので刑事が単独で聞き込みや調査をおこなうことはイレギュラーだと思いますが、物語の都合上、そういうケースが多く見られるのがリアリティさに影を落としています。
★★☆
◇著者別読書感想(中村文則)
【関連リンク】
12月前半の読書 帰還、探偵の流儀、眠り姫(上)(下)
11月後半の読書 クロイドン発12時30分、流人道中記、2035年の世界地図、歴史とは靴である
11月前半の読書 片腕をなくした男、凍りのくじら、ニッポンの闇、ワイルドドッグ路地裏の探偵
| [PR] Amazon 医薬品・指定医薬部外品 売れ筋ランキング | |||
鼻水・鼻炎 便秘改善 肌・皮膚トラブル改善 |
睡眠改善 関節痛・神経痛 肩こり・腰痛・筋肉痛 |
胃腸改善 整腸剤 喉・口中改善 |
目薬 育毛・養毛剤 痛み止め |
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
1869
帰還(文春文庫) 堂場瞬一
というのも著者の小説ではシリーズものが多く、その中でも初期の「刑事・鳴沢了シリーズ」は外伝以外、すべて購入して読みました。
「刑事・鳴沢了シリーズ」はとても面白かったのですが、その後のシリーズ「警視庁失踪課・高城賢吾シリーズ」は、一部だけ読むに留まっています。
とにかく多作な作家さんで、次々と新作が出てくるので、少々飽きてきたのと、できるだけ多様な作品を読みたい派なので、しばらく(15年ほど)ご無沙汰していました。
元々は読売新聞社で記者をしていた経験がある著者なので、新聞記者の習性や、社内の事情などには明るく、それが小説の中でもよく生かされています。
著者が勤務していた時代から20年以上経っているので、大きく変わっていると思われますが、そこは元同僚や部下達が今では偉くなっているでしょうから話を聞いて調べることも容易でしょう。それだけ新聞社の様々な事情は真に迫っていて、そこまで詳細に書くか?と思うほどでした。
全国紙の社員なら、30年前までなら銀行や総合商社に劣らず高給&好待遇だったと思いますが、現在では衰退産業のひとつで、いろいろ厳しいようです。
内容は、30年前に同期として入社し、当時同じ支局に配属された4名のうちのひとりが、四日市支局で水死する事故で亡くなります。
その事故に疑問を感じ、またどうして四日市支局へ配属希望を出したのか?など不自然な行動を本来の仕事とは関係がない記者が調べていくというものです。
久しぶりに読んだ著者の作品ですが、持ち前の切れ味は今でも健在で、とても面白く読めました。
★★☆
◇著者別読書感想(堂場瞬一)
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
探偵の流儀(光文社文庫) 福田栄一
東海地区の30万人都市にある探偵事務所が舞台で、所長以下、2名の探偵と1名の事務員(バイト)だけという零細事務所で、失踪人探しや迷い犬の探索などなんでも引き受ける地元密着の探偵事務所です。
ある女性の行動調査中に所長が階段から転落し意識不明の重傷を負います。仕事の多くは所長の人間関係で受注しているので、所長がいなくなると探偵事務所の存続が危うくなります。
探偵のひとりは元警察官で、あるミスから辞職に追いやられてしまった過去を持っていますが、その時の上司と同僚が、警察を辞めて別の大手調査会社に転職しライバルとなって現れるというややこしい事態になっていきます。
しかしわずか人口30万人の地方都市で、複数の正社員の探偵を抱える個人探偵事務所の経営が成り立つのか?という素朴な疑問もありますが、そこは小説なので。
もうひとりの探偵の過去や意識不明の重傷を負った所長のその後など、謎がそのまま不明のままで、事件は解決し終わりましたので、これは続編がありそうだと思いましたが、解説でもそれに触れてありました。
その続編は2015年に出版された「森笠邸事件 探偵の流儀II」ですが、AmazonではKindle版しか見つかりません。
★★☆
∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
眠り姫(上)(下)(ダニエル・キイス文庫) ダニエル・キイス
この作品は、1998年出版の小説で、原題は「Until Death Do us Part」(死が二人を分かつまで:結婚式の誓いで使われる常套句)で、主に精神病と死刑制度、睡眠障害と催眠療法などが主なテーマとなっています。
眠り姫と言うと、ヨーロッパの童話でシャルル・ペローの「眠れる森の美女」やグリム童話の「茨姫」などが思い出されますが、この小説の主人公の女性が若い頃から睡眠障害で、突然どこにいても寝てしまう障害があり、「眠り姫」と呼ばれていることからタイトルは来ています。
サスペンス小説では珍しく、なにが起きたかは最初のほうで出てくるので書いてしまいますが、あるとき主人公の女性が、正気でない時に我が子の娘とそのボーイフレンドを射殺してしまいます。
それを目の当たりにした夫が、真実を隠し、妻を守るため、二人の死体を川に捨て、拳銃に自分の指紋を付けて川のそばに埋めます。
警察の捜査で、夫が殺人犯として裁判で有罪となり死刑が確定しますが、同時に精神的に不安定でそのような場合に死刑が執行できるのかどうか問題になってきます。
もうひとりの主人公、精神科医の女性が睡眠暗示を駆使し、死刑囚の精神病を改善しようとしますが、、、
実は一般的に知られている童話の「眠れる森の美女」はハッピーエンドに変えられていますが、元の話は睡眠中のレイプなどとてつもなく残酷な内容です。それもモチーフとして使われています。
割と分厚い文庫で上下巻ありますが、登場人物は少ない上に、文字は大きく読みやすく、前半をしっかり読めば、後半はその半分の時間でサクッと読めます。
★★☆
◇著者別読書感想(ダニエル・キイス)
【関連リンク】
11月後半の読書 クロイドン発12時30分、流人道中記、2035年の世界地図、歴史とは靴である
11月前半の読書 片腕をなくした男、凍りのくじら、ニッポンの闇、ワイルドドッグ路地裏の探偵
10月後半の読書 八甲田山 消された真実、四人組がいた。、人類の終着点、凍原
| [PR] Amazon 医薬品・指定医薬部外品 売れ筋ランキング | |||
鼻水・鼻炎 便秘改善 肌・皮膚トラブル改善 |
睡眠改善 関節痛・神経痛 肩こり・腰痛・筋肉痛 |
胃腸改善 整腸剤 喉・口中改善 |
目薬 育毛・養毛剤 痛み止め |
リストラ天国TOP
おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX)
著者別読書感想INDEX
|
カレンダー
|
|
最新記事
|
(02/07)
(01/24)
(01/17)
(01/10)
(01/03)
(12/27)
(12/20)
(12/13)
(12/06)
(11/29)
|
カテゴリー
|
|
ブログ内検索
|
|
最新コメント
|
[06/28 area]
[06/28 U・M]
[01/03 area]
[01/03 Anonymous]
[10/09 area]
|
プロフィール
|
HN:
area@リストラ天国
HP:
性別:
男性
趣味:
ドライブ・日帰り温泉
自己紹介:
|
過去人気記事
|
医者と作家の二刀流一覧
日本の農業はどこへ向かうか
ロバート・B・パーカー「スペンサーシリーズ」全巻まとめ
マイカーで東京から京都まで旅行する場合 その1
リタイア後の心配事
有効求人倍率がバブル時並みとは
スペンサーシリーズの読み方(初級者編)
年賀状と葬儀について
ガソリンスタンドのブランド変遷史
世界と日本の宗教別信者数
戦国武将たちの身長は?
証明写真機の種類と機能を調べてみた
ゴルフをプレイしている人の年代層割合に驚いた
活字離れは事実か?
サイコパスたちの宴
世界と日本の書籍ベストセラーランキング
変形性股関節症の人工股関節全置換手術
Amazon 売れ筋ランキング ドライブレコーダー レーダー探知機 空気清浄機 ペット用品 まくら・抱き枕 体脂肪計 スポーツウェア ランニングシューズ メンズスニーカー レディーススニーカー ゴルフクラブ ゴルフシューズ ミラーレス一眼カメラ ゲーム ノートパソコン プリンタ イヤホン・ヘッドホン スマートフォン スマートウォッチ microSDカード 防犯カメラ スペシャリティアパレル ラーメン レトルト・料理の素 シャンプー・コンディショナ スキンケア・ボディケア |
